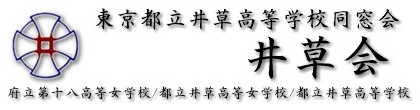寒締めホウレンソウーお天気百話⑫
冬、つくばにある野菜直売店では、「寒締めホウレンソウ」が並びます。この「寒締めホウレンソウ」は、通常のホウレンソウと比べると、葉や茎が縮んでいるためにしわしわとして肉厚ですが、柔らかく、色の濃いことが特徴です(写真1)。また、食べてみるとホウレンソウ特有のえぐみが少なく、強い甘みを感じます(農林水産省)。この「寒締めホウレンソウ」は、通常のホウレンソウと同じように冬の季節ではハウス内で栽培しますが、収穫の10日~14日前頃からハウス内を換気することによって、氷点下の厳しい寒さにさらします。これが「寒締め」といわれる所以です。産地には青森県、岩手県、そして北海道などがあります。

写真1.ハウス内での「寒締めほうれんそう」の栽培風景.このハウスがある岩手県八幡平市西根地区は、ほうれんそうの生産量では岩手県内でトップクラスを誇る(ハチクラWebより).(写真提供は伊藤ゆみさん).
ホウレンソウの甘みが増すのは、寒さから身を守るための変化です。ホウレンソウの体内は90%近くの水分で占められており、細胞内(細胞質)と細胞間隙(細胞質を覆う細胞壁の外の空間)に分布しています。そして、細胞が正常に機能するためには細胞内と細胞間隙に含まれる水分のバランスが重要です。
ところが、霜がおりるような厳しい寒さにさらされると、細胞間隙の水分が凍結しやすくなります。すると、細胞内と細胞間隙との水分のバランスが崩れて、水は細胞内から細胞間隙に移動するので、細胞内は必要な水を保持できなくなります。このような水の移動を抑えるために、細胞内は糖やアミノ酸などの濃度を上昇させることで、細胞内と細胞間隙との水分のバランスを保とうとします。また、この時、細胞内では水の凝固点が下がるので水分が凍結しにくくなります。
なぜ、細胞内の糖やアミノ酸などの物質の濃度を上昇させると、水分が凍結しにくくなるのか。それは、「モル凝固点降下」という現象によるものです。この「モル凝固点降下」という言葉は初耳に感じられるかもしれませんが、みなさんの多くが井草高校時代の化学で学んだ用語です。通常、水分は0℃で凍結しますが、糖などの物質の濃度が高くなると、凍結する温度が0℃よりも低くなるのです。そのため、糖分などの物質を多く含んだ水分は、ある程度の低温になっても凍らないのです。
さて、この肉厚で甘みの強い「寒締めホウレンソウ」を、どのようにおいしく味わうことができるでしょうか?加熱調理すると甘みが一層増すことから、おひたし(写真2)や卵とじにすると、甘みだけではなく、色と肉厚の「食感」を味わうことができます。また、茹でたものをオリーブオイルで炒めて、これを肉料理の付け合わせにすると、鮮やかな緑色と焼き肉の色とのコントラストを楽しむことができます。

写真2.「寒締めホウレンソウ」から調理したおひたし(渡部京子さんの提供).
ペンネーム:つくばのトリさん
井草高校27期D組の卒業生です。
地図と時刻表をもって旅行することが好きで、高校時代は山岳部に所属していました。
その後、大学で気象・気候学の面白さを知り、その延長線で気象・気候に関係する職業に携わったので、茨城県のつくばに住んでいます。
これからも、どうかよろしくお願いします。
詳しくは、私のブログ「圃場管理のための気象のお話」の「著者プロファイル」をご覧ください。