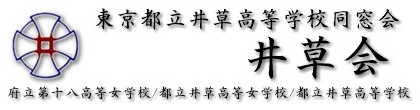哺乳類の保全を巡ってー奄美大島のマングース根絶(その1)
奄美大島のマングース根絶(その1)
1970(昭和45)年に井草高校を卒業(22回生)。高校では生物部に所属していました。このコラムでは、哺乳類の生態と保全を巡る話題を主に取り上げていきたいと思います。
昨年(2024年)9月3日、環境省は特定外来生物(*1)フイリマングース(以下マングース)の奄美大島(712平方キロメートル)からの根絶を宣言しました。人が暮らすこれだけ大きな島でマングースの排除が達成されたことは世界的にも画期的な成果です。今回と次回で、私が30年近くかかわってきた、奄美大島におけるマングース防除の経緯を紹介します。
正式な記録はないのですが、マングースがハブ対策として奄美大島に持ち込まれたのは1979年とされます。しかし昼行性のマングースが夜行性のハブを減らすことはなく、個体数の増加と分布域の拡大に伴って1990年頃には農作物や家禽の食害が問題化し、1993年度から、鳥獣保護管理法に基づき、有害鳥獣として駆除(2003年度で終了)が行われるようになりました。
マングースは、主に19世紀の終わり頃、サトウキビ畑に害をなす外来ネズミ対策として西インド諸島やハワイ諸島などに導入され、多くの在来動物の減少・絶滅を引き起こしました。固有希少種の多い奄美大島(2021年に自然遺産登録)でも同様の事態が起きると懸念されたことから、環境庁(当時)は、生息状況の把握や対策の検討を目的として、1996年度に調査事業を開始しました。
調査の結果、1999年度の時点で、マングースは島の約4割まで広がっていること、在来の哺乳類、鳥類、爬虫両生類の捕食が確認されたことなどから、一刻も早い対策の必要性が明らかになりました。また、個体数が約5千から1万頭と推定されたのに対して、1999年度には2千頭以上がわなによって捕獲できたことから、捕獲努力の増強による根絶可能性も示唆され、2000年度から環境庁による「駆除事業」が始まりました。
次回に続きます。
*1 外来生物の中で、特に生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、あるいはそのおそれがあるもの。外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づいて指定される。
プロフィール:石井信夫(22回生)1952年東京生まれ。東京大学大学院農学系研究科修了(農学博士)。自然環境研究センター、東京女子大学に勤務。東京女子大学名誉教授。