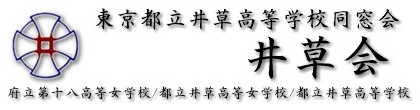2025年度OB/OG会-生物部
開催日:2025年6月9日(日)
場 所:上野 東京国立科学博物館
参加者:7名(男5、女2)
例年恒例となった生物部OB・OG会の初夏の集いが、今年は国立科学博物館で開催されました。今回の訪問では、1970年卒業の先輩である石井信夫先生にガイド役を引き受けていただきました。石井先生は東京女子大学名誉教授で、哺乳類学の専門家の視点から展示の解説をしていただける貴重な機会となりました。
まず日本館に入り、石井先生はイギリスなどに比べて日本には固有種(そこでしか見られない生物種)が多いことを強調されました。「津軽海峡を通る動物相の分布境界線」の展示では生物の剥製を見ることにより、生息している生物の違いが印象に残りました。津軽海峡を境に北と南で生物相が分かれる様子が詳細に展示されており、日本館のウェブサイトには「ブラキストン線」として知られるこの境界線が日本の生物多様性を形作る重要な要素です、との解説がありました。また、1912年に渡瀬庄三郎が提唱した屋久島・種子島と奄美諸島の間にあるトカラ海峡に引かれた生物地理学的境界線である渡瀬線についても解説がありました。
地球館では、日系二世のワトソン T. ヨシモト氏が寄贈された剥製コレクションの展示に時間を費やしました。世界各地の大型哺乳類の標本が一堂に会するこの展示について、石井先生は「全て一緒に展示されているので、個々の動物の分布と分類がもっと分かりやすくなっていると良いと思います」と専門家ならではの視点を示してくださいました。
この展示を見ながら、博物館のジオラマ製作を見ているときに、かつて読んだニューヨークタイムズの記事を思い出しました。その記事ではアメリカ自然史博物館でジオラマ制作に携わる専門家、ステファン・クリストファー・クインが取り上げられていました。彼は、ミュージアムアーティストとして、動物の自然な生息環境を再現するジオラマの背景を手がけ、多くのプロジェクトに貢献したことで知られています、とありました。このような専門家の存在を知り、博物館展示の奥深さに新たな関心を抱きました。博物館の展示も「研究」と同様に進歩を続ける、ということを体感する経験でした。
地球館の生物の歴史の展示を見学したときには、最近の研究についての記事を思い出しました。それは、約2億3200万年前を中心とした中生代三畳紀の「カーニアン多雨事象」と呼ばれる気候現象についての研究成果でした(注)。この約200万年続いた異常な多雨期が、当時まだ地球上の主要な陸上動物ではなかった恐竜たちの急速な種分化と繁栄のきっかけとなったという記事の説明には、興味をひかれました。展示と最新の研究成果を結びつけることで、生物の歴史の理解がさらに深まったと感じました。
博物館見学後の懇親会では、やはり生物に関連する話題が多く話されました。印象的だったのは、ある参加者が最近視聴した人体に関する科学番組の話題でした。細胞内で物質を運ぶモータータンパク質であるダイニンとキネシンの活動を示す精緻な動画について、「細胞内でこんなに様々な活動が営まれているとは想像できなかった」と語っていました。
今回の訪問を通じて、自然の神秘に対する好奇心の高校時代からの変わらなさを再確認できました。幹事の方のご尽力と、共有される科学への興味が、私たちOB・OG会の絆をさらに深めてくれています。なお、今回の参加者は、1970年、1971年、1972年の卒業の7名のOB・OGでした。
次回の生物部OB会活動は秋の井草祭訪問を予定しています。高校時代の思い出の場所で、現役生徒たちの活動を見学する機会として、多くのOB・OGの参加をお待ちしております。
(注) 論文情報
タイトル
“Marine osmium isotope record during the Carnian “pluvial episode” (Late Triassic) in the pelagic Panthalassa Ocean”
DOI
10.1016/j.gloplacha.2020.103387
著者
Yuki Tomimatsu, Tatsuo Nozaki, Honami Sato, Yutaro Takaya, Jun-Ichi Kimura, Qing Chang, Hiroshi Naraoka, Manuel Rigo, Tetsuji Onoue
掲載誌
Global and Planetary Change (2020年11月25日版)
2020.12.08 神戸大学 プレスリリース
大量絶滅と恐竜の多様化を誘発した三畳紀の「雨の時代」
日本の地層から200万年にわたる長雨の原因を解明
https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2020_12_08_01/