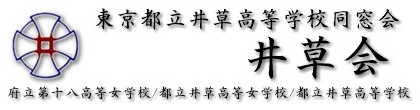哺乳類の保全を巡ってー外来種問題(その2)
外来種問題(その2)
外来種対策については、すでに人為によって変化した、手付かずの状態ではない自然を膨大なコストをかけて守る意味はあるのかという意見もあります。しかし、このことには文化財や遺跡、歴史的景観の保存と似た面があり、残された自然遺産をできるだけ損なわず次世代に引き継ごうとするなら、侵略的外来種の排除は避けて通れません。
定着した外来種の制御・根絶はうまくいかず、期待されたような結果は得られないことが多いという指摘もあります。確かに、外来植食者(植物食性の動物)の駆除によって外来植物が繁茂する場合や、外来捕食者を排除することで、捕食されていた別の外来種が増加する場合があるので、話は簡単ではありません。しかし、奄美大島のマングース防除事業のように、外来種の制御・根絶によって在来種や生態系が回復する事例は多く、また、期待に反することが起きたならば、自然をより深く理解し、新たな方策を考える機会とすることができます。
栽培・観賞植物や家畜・家禽・愛玩動物はほとんどが外来起源であり、外来種を利用しなければ人間社会は成り立ちません。また、すでに膨大な数の外来種が定着していて、今後も新たな移入・定着は続くでしょう。外来種をすべて排除するという考えは現実的ではありません。影響のとくに大きい一部の外来種について対策をとろうということなのです。
人間の都合で持ち込まれ、問題を起こすと排除される生き物に対しては申しわけない気持ちになりますが、対策を取らなければ私たちは実に多くを失うことになります。できるだけ早く制御・根絶することが外来種、そして在来種の犠牲を少なくすることにつながります。
外来種対策は、希少種や生態系の保全を目的としているケースもありますが、実際のところは、アライグマやタイワンリスなど、農林水産業被害、生活被害(家屋の汚損など)を防止するため必要に迫られて行われているもののほうが多く、人間社会に直接影響するような被害の対策はいずれにしても避けられません。
前の回で述べたような、外来種問題にかかわる国際条約や国内法が制定されていることは、外来種対策の必要性に関する明確な社会的合意の存在を示しています。そしてそれは、生物多様性がもつ様々な実用的・非実用的価値をふまえて、私たち人間にとって望ましい自然を維持・回復・利用するための合意であり、人類の身勝手と言えます。しかし、在来の生物種や生態系に価値を認め、次世代に引き継ごうとするなら、他にやり方はないのが現実です。
基本的に、外来種対策への着手は早ければ早いほど良く、遅れるほど対処に要する時間、コスト、そして外来種の個体数は増加します。しかし、問題が顕在化する前に予算を確保することは難しく、被害が許容レベルを超えるまで放置され、それから対策が始まることが多いのが現状です。
こうした状況を変えていくために、外来種問題については、生物多様性の保全という理解しにくい面だけでなく、農林水産業・生活・文化財被害といった身近な被害の実態、外来種対策の意義、これまでの内外の成果について積極的に情報提供し、一般にもっと広く周知することが必要だと私は考えています。
なお、人間社会の問題が外来種問題になぞらえて議論されることがあります。ここでは、ヒトという単一の生物種に属する個体(個人)あるいは集団間の問題と、異なる生物種間の問題とを混同すべきでないということだけ指摘しておきます。
プロフィール:石井信夫(22回生)1952年東京生まれ。東京大学大学院農学系研究科修了(農学博士)。自然環境研究センター、東京女子大学に勤務。東京女子大学名誉教授。